結果を出すリーダーはみな非情である
明治維新も第2次大戦後の復興も、革命の担い手はいつの時代も、企業でいえば課長クラスのミドルリーダーだ。日本企業や日本社会も今の混迷期を脱するには、ミドルリーダーの踏ん張りが欠かせない。社長も含めて上司はコマとして使い、最大の成果を上げる程度のハラは必要だ。自分がトップのつもりで考え行動するリーダーにとって不可欠な、合理的思考とそれに基づく意思決定力の鍛え方とは?
明治維新も第2次大戦後の復興も、革命の担い手はいつの時代も、企業でいえば課長クラスのミドルリーダーだ。日本企業や日本社会も今の混迷期を脱するには、ミドルリーダーの踏ん張りが欠かせない。社長も含めて上司はコマとして使い、最大の成果を上げる程度のハラは必要だ。自分がトップのつもりで考え行動するリーダーにとって不可欠な、合理的思考とそれに基づく意思決定力の鍛え方とは?
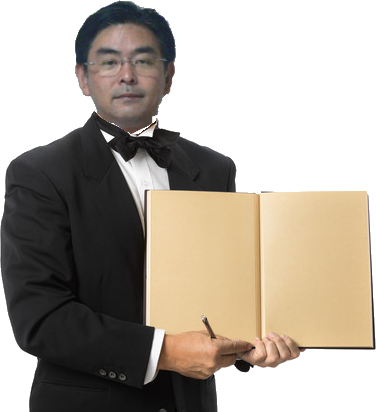
一人ひとりの働き方や生き方は、今後どう変わっていくのか?より充実したものにするには何が必要なのか?働く人(生活者)と働いてもらいたい人(経営者)が答えをだす時期が来ている。今までの日本、これからの日本を政治に押し付けず、自らの責任として真剣に考えなくてはならない。
他サイト情報の引用
あるプロジェクトを進めるうえでは、そのチームメンバーに属する者は上司であろうと部下であろうと成功に向けた駒だと考えるべきである。常に、目指す成果を得るためには何をすべきか、という“社長”の目線で考え、取り組もう。
欧米や新興国のように、年齢に関係なく出世が決まる世の中になると、自分より年上の部下を使わなくてはならない場面が増えてくる。「そういうときは、何に注意すればよいですか」という質問を受けることがあるが、基本的に年上も年下も関係ない、と私は思っている。
役職に関しても同じことで、自分の部下をマネジメントするのも、上司をマネジメントするのも同じことである。より正確に言うなら、上司も部下も含めてプロジェクト達成のためのひとつのチームであり、そのメンバーをいかにマネジメントしていくかが大切なのである。
1つのプロジェクトを動かすときに、たとえば予算権限を自分の上司が握っているとしたら、その“大蔵省”である上司もチームメンバーと捉えるべきである。大きなプロジェクトになれば、関係部署も増え、稟議書に判子をもらわなければならない管理職の数も増えていく。その人たちと自分の部下を合わせて、全部をプロジェクトチームと考えるのだ。
組織のヒエラルキーというものを絶対視し過ぎると、そういう発想でプロジェクトを柔軟に動かしていくことができなくなる。仮に、課長である私と部長である上司との関係が逆転したらどうしよう……などということは、端から考えてはいけない。
逆に、部下だと思って油断したり、不遜な態度を取ったりするのも愚かしい行為だ。とにかく、部長であろうと社長であろうと、プロジェクト達成に向けた自分の駒だと考える。客先に社長を引っ張り出したほうがプロジェクトがスムーズに進むと思ったら、土下座してでも社長を連れて行くべきなのである。
チームメンバーをどう動かすかというときに重要なのは、メンバー一人ひとりの癖や性格、抱えている利害関係と社内的立場、あるいは人間関係、そういった情報なるべく多く事前にインプットしておくことだ。
相手のことをよく知っておかないと、うまくハンドリングはできない。それは相手が部下でも上司でも、本質的には同じなのである。
(次回は11月1日更新予定です。)